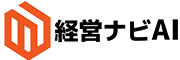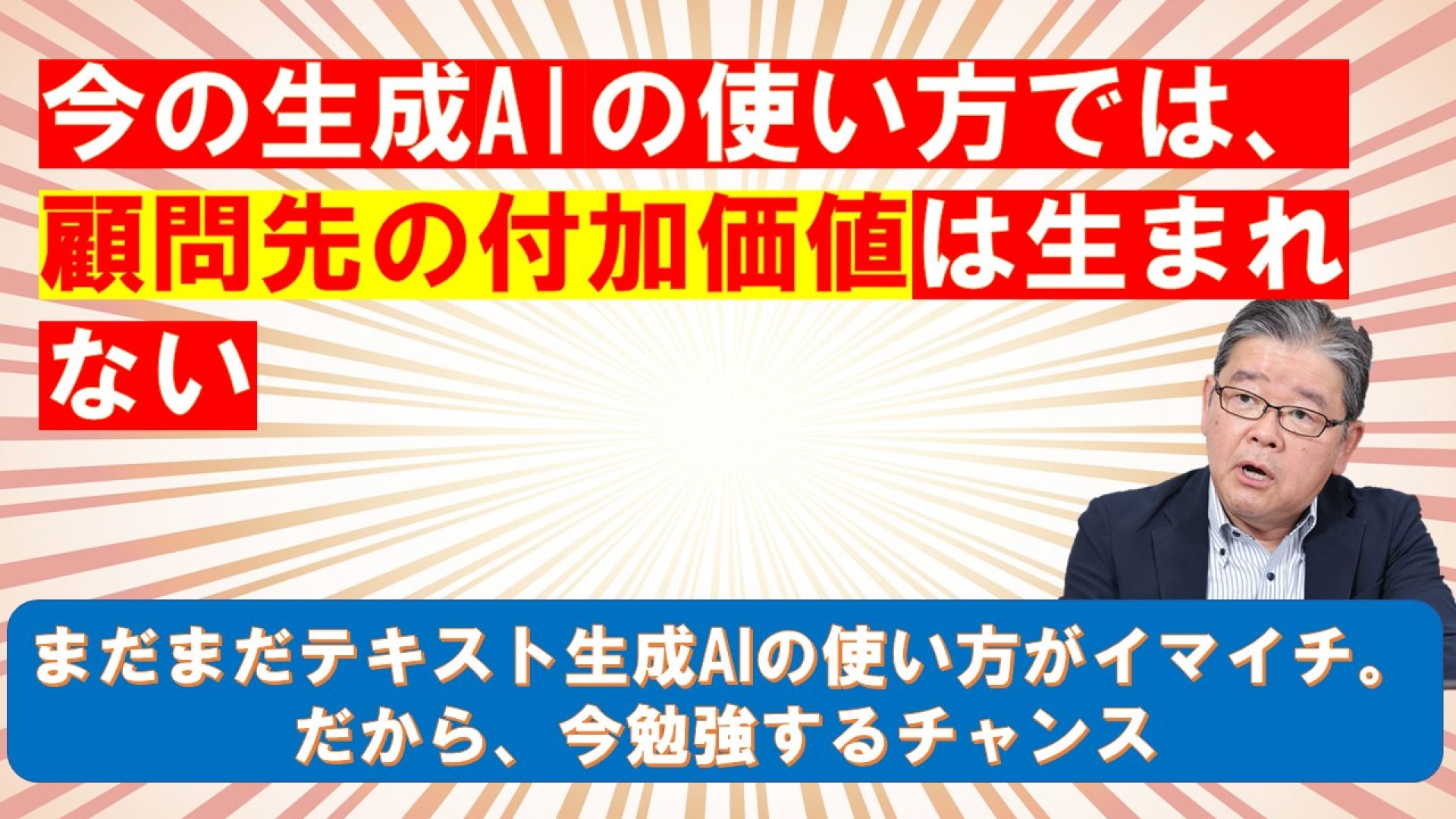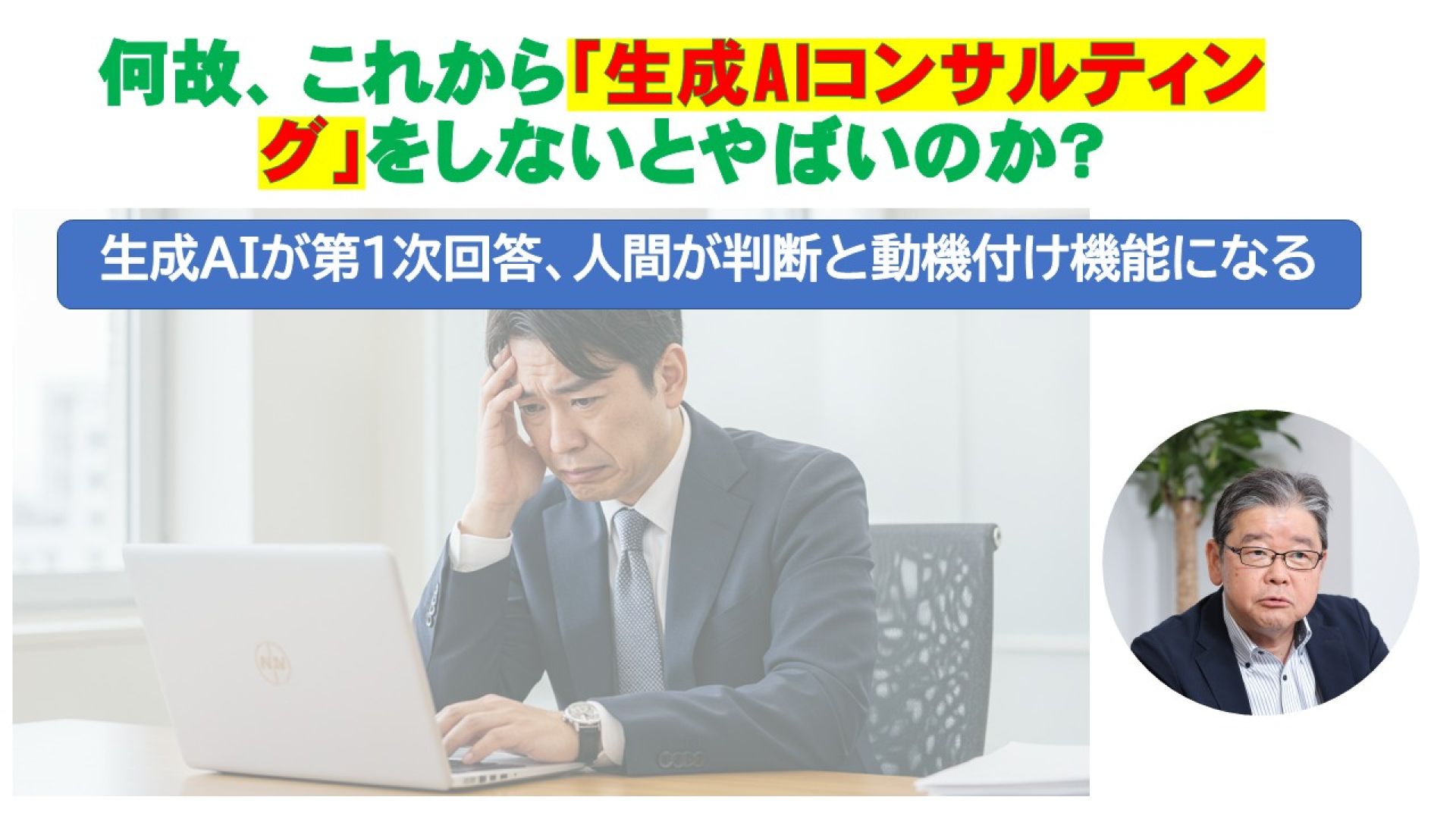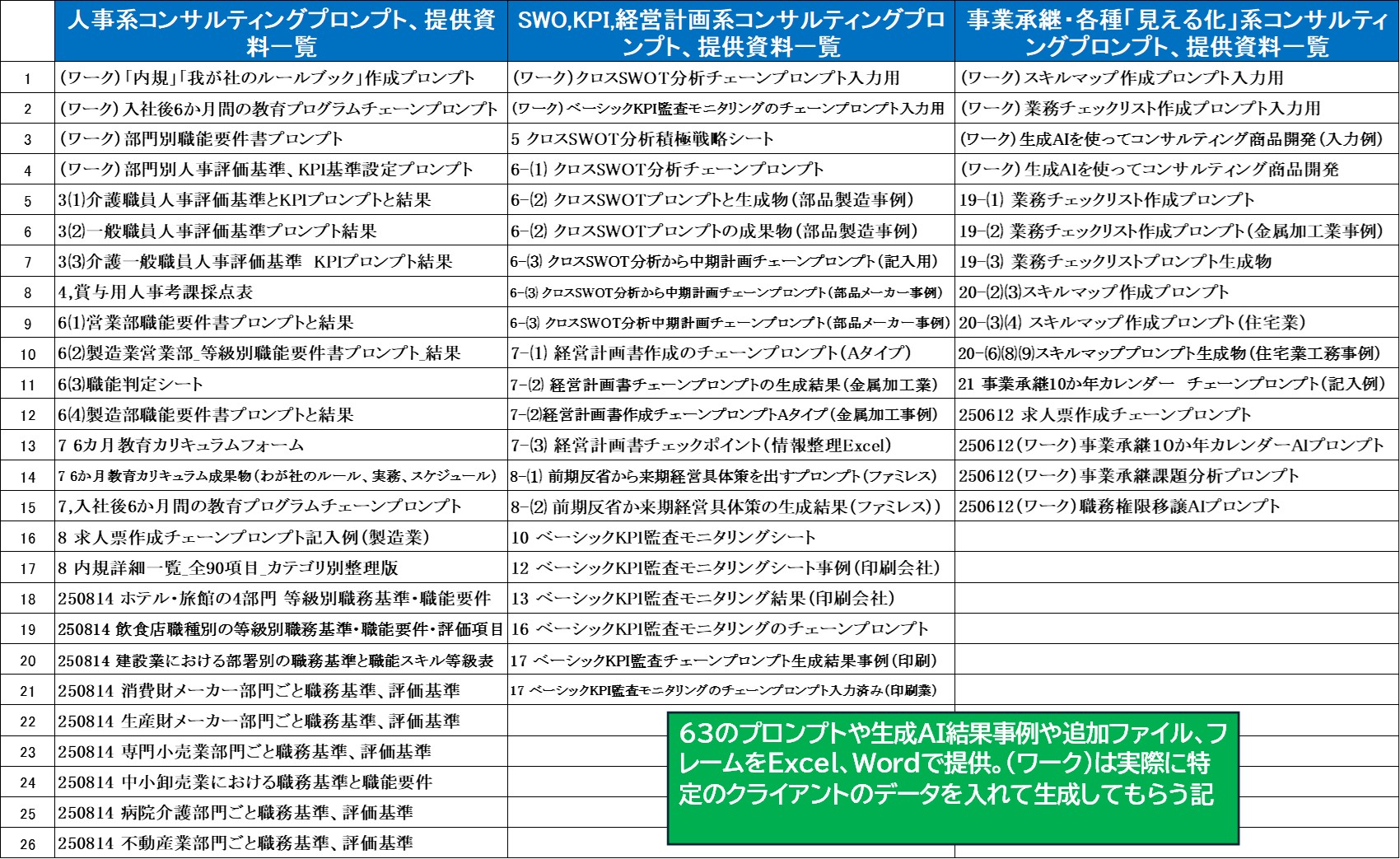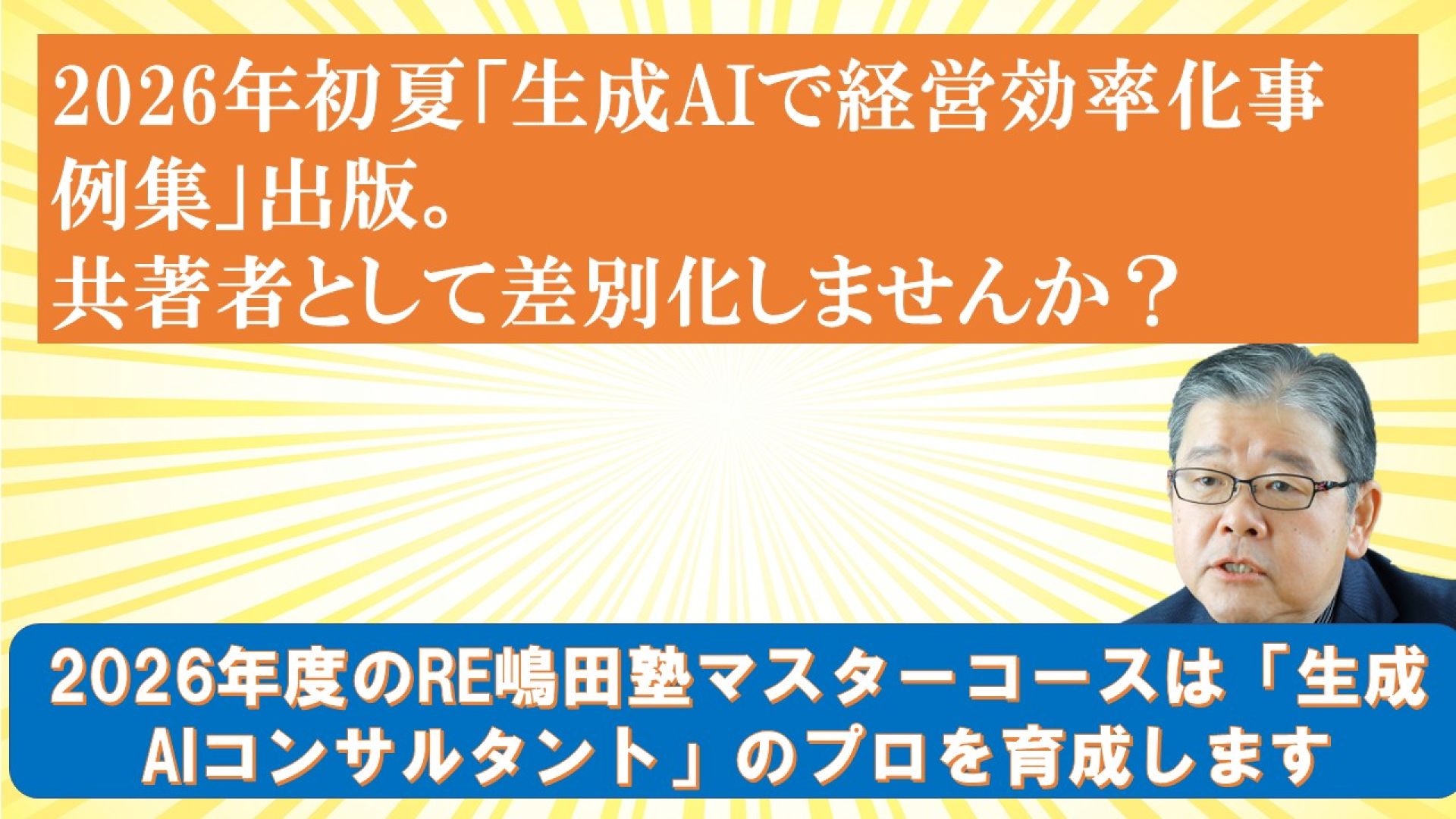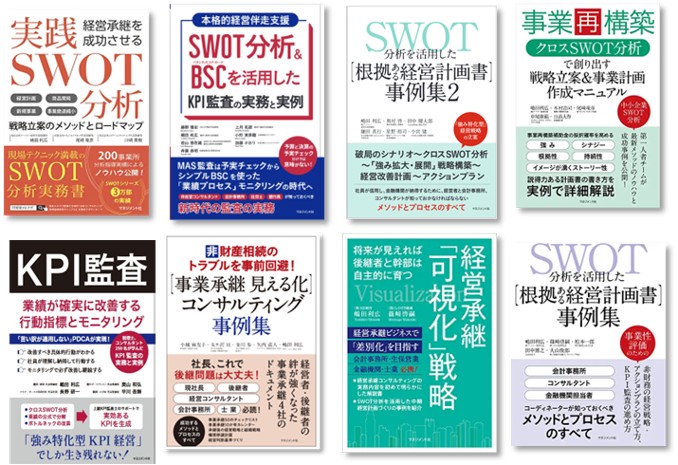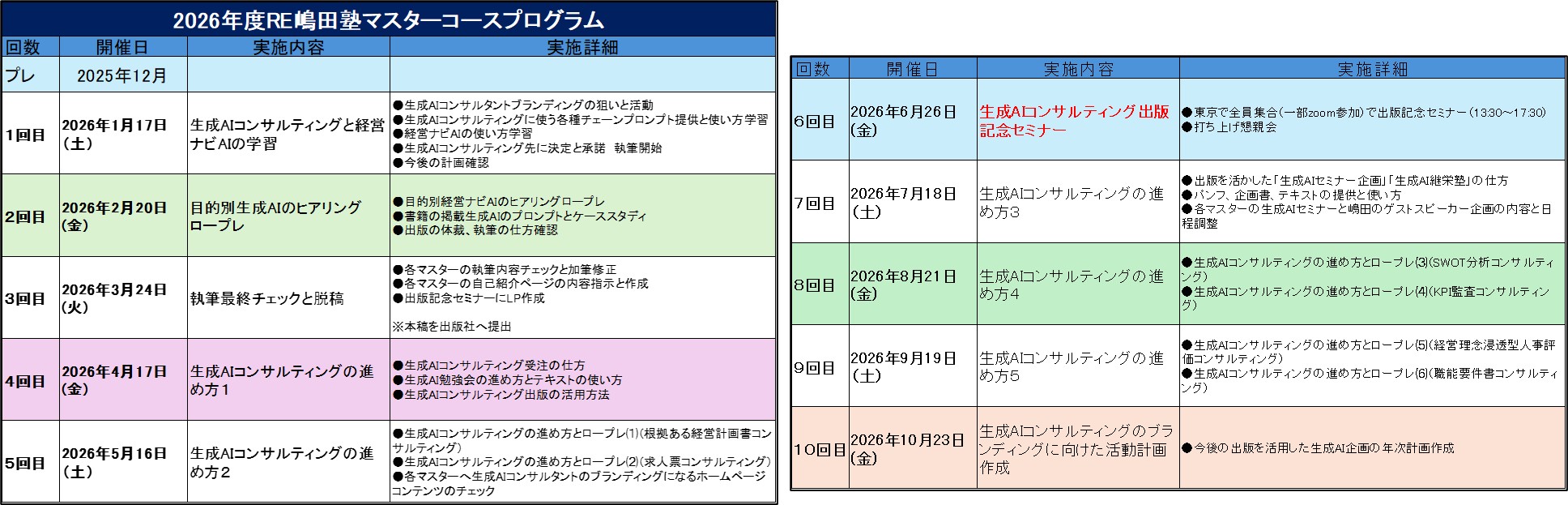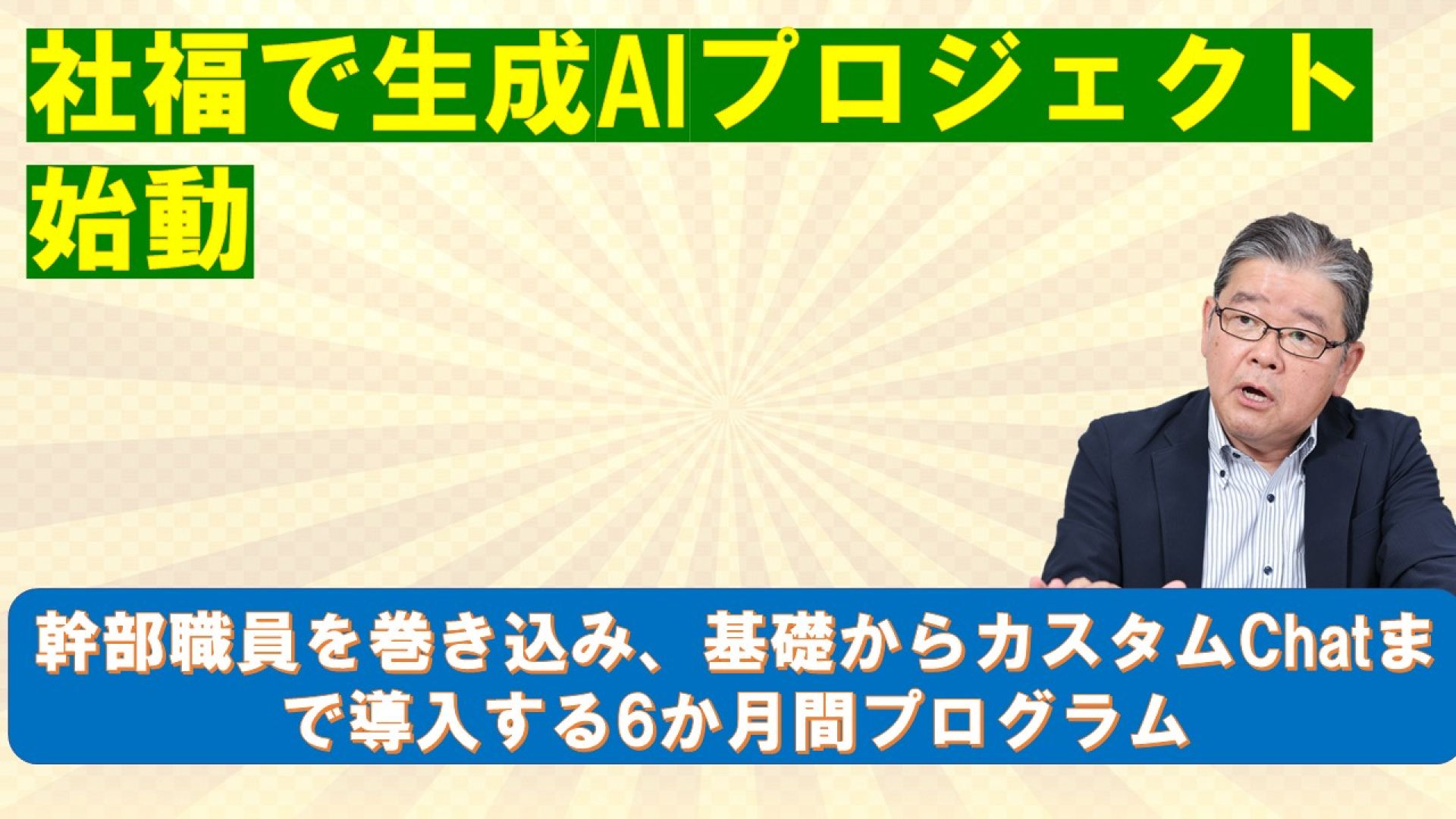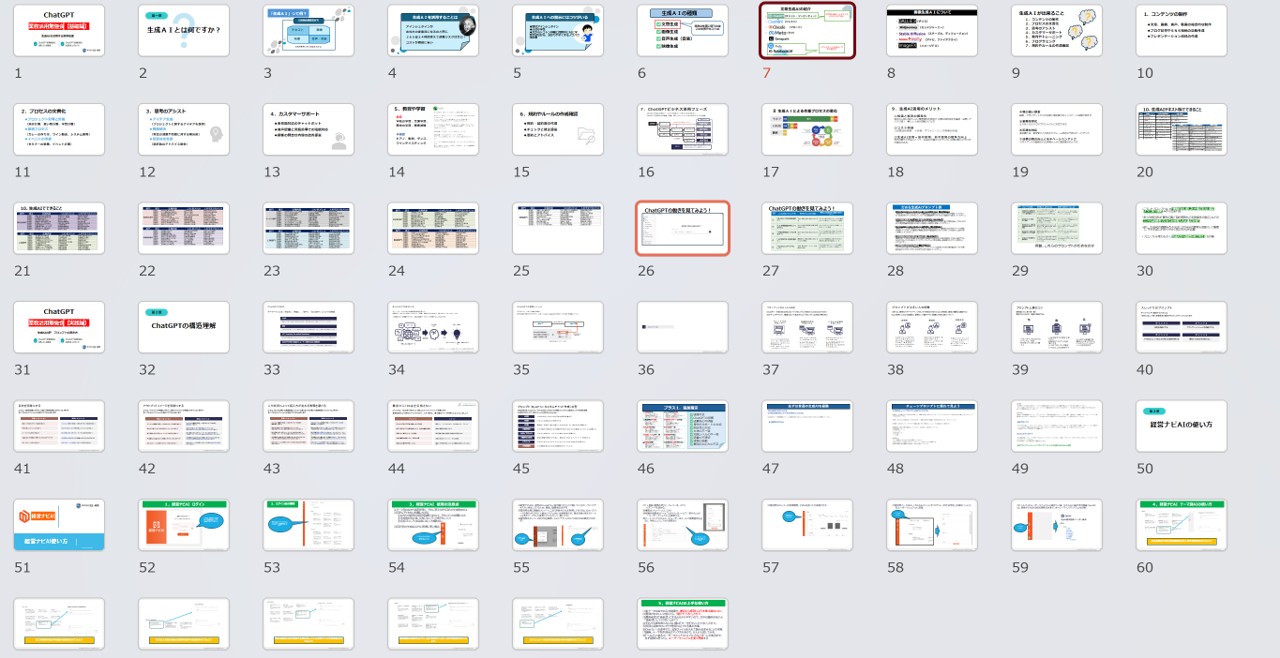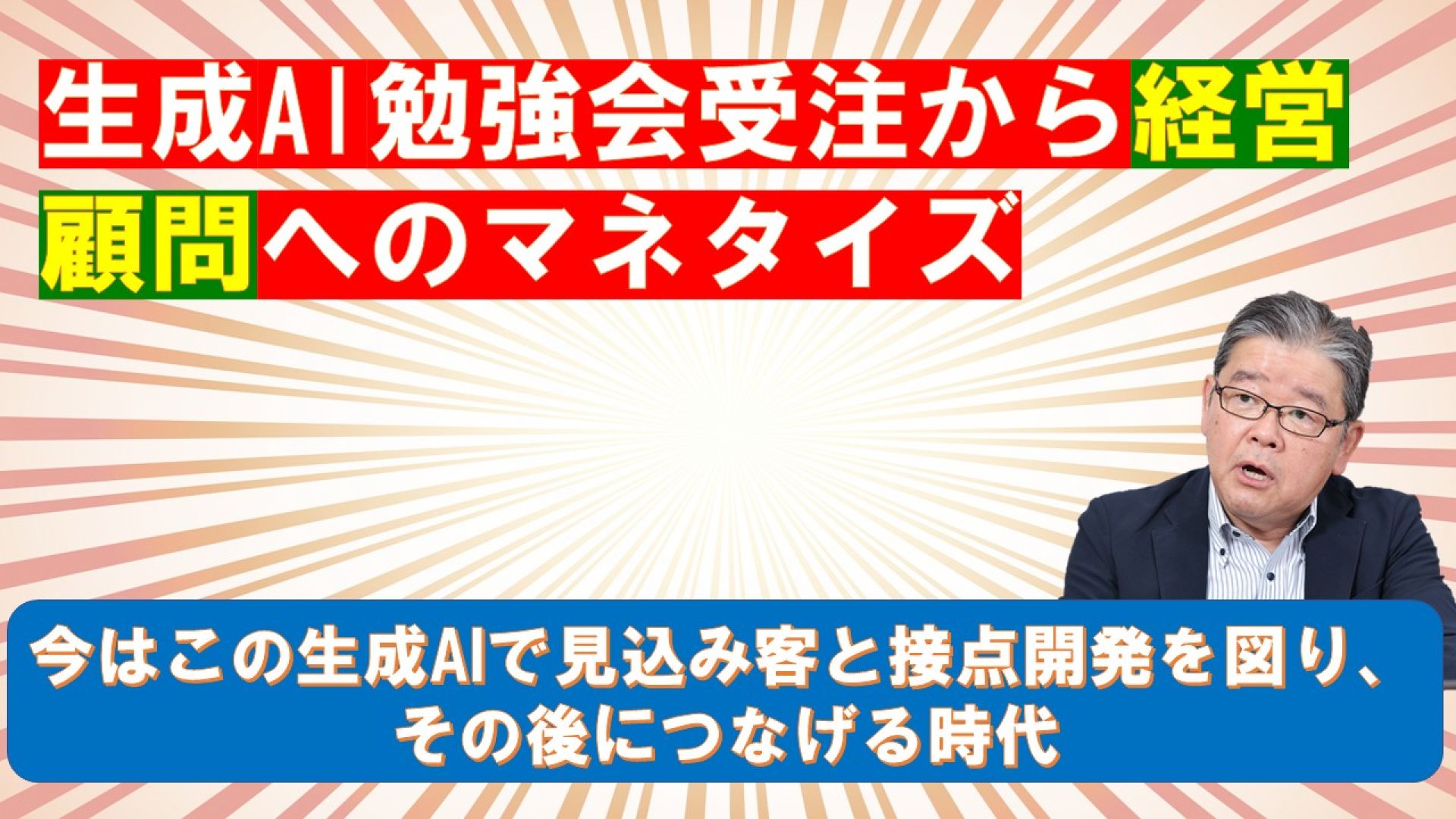9月11.12日の「会計事務所博覧会2025」に出展して、いろいろな会計事務所の方や金融機関の方、既に当社とお付き合いのある税理士の方は当社のブースにお越しになり、情報交換をしました。
今回のタイトルである「生成AI活用」は会計事務所の生命線になるかもしれません。
そう感じたのには理由があります。それはいくつかの会計事務所や金融機関の方から博覧会で直接聞いた話です。
●生成AIが波及する自分たちの業務が楽になると同時に、付加価値を出さないとやばくなる
●これまでMAS業務(経営支援)には消極的だったが、そうも言っておられない状況だ
●生成AIでコンサルティングをする場合、どんな形式になるのか教えて欲しい。うちの事務所は各方面で生成AIに詳しい事を今のうちからブランディングしたい。
金融機関の方からは、
●AIで事業計画書の素案が迅速にできれば、融資の稟議も早くできる
●自分達は生成AIを使って業務ができないから、無料版の範囲で事業計画などのアドバイスもしたいのだが・・・
今回の会計事務所博覧会のメインテーマに、多くの方が興味を持っているのです。
しかし、思いとは裏腹に「効果的な生成AIの使い方」ができてない会計事務所も多く、さらに中小零細企業の経営者にも、まだまだ意識が低い方が多いのが、日本の実情です。
1,Google検索の延長線上の使い方では効果薄
「うちの事務所は生成AIをいつも使ってますよ」
ある税理士所長がこう胸張っていました。で実際の使っている内容を聴いていと、単発プロンプトで、知りたい情報を生成させる事はほとんどでした。
これなら「Google検索の延長線上」で、「検索サイトのバラバラの情報が整理されて見れるから、楽だ」程度の感覚です。
生成AIは生成AIたる所以は「推論」する事です。
いろいろな情報を与え、こちらの目的に沿うようなプロンプトを絞り込み、生成AIが回答を出す。
しかも段階的に学習させながら行う事に効果があるわけです。
ですが、多くの場合「単発プロンプト」でAIが何らかの答えを出す事で満足したり、納得している。
これだと、いずれ顧問先経営者も単発プロンプトでいろいろな課題解決で生成AIを使うようになると、会計事務所に生成AIの使い方を聴くことはなくなります。
会計事務所が使う生成AIは自業務の簡素化やパターン化、時短には有効でも、「経営支援業務」では、いまいち評価されないのです。
我々が口を酸っぱくするほど、会計事務所に伝えているのは生成AIのプロンプトは「単発プロンプト」ではなく、「チェーンプロンプト」や「Chatリレー形式」のプロンプト技術です。
この技術がなければ、生成AIの経営支援での活用も成果も表面的なものでしかありません。
この辺りのノウハウも今後、ご紹介していきましょう。
2,中小企業経営者が生成AIに本気で取り組まない理由
もう一つの課題が中小企業経営者も生成AIの活用にそこまで前向きではない方が多いという事です。
確かにハルシネーション(事実に基づかない情報)とかセキュリティがどうとか、どうせ一過性のブームだろうとか、いろいろ使わない理由はあります。
しかし、これはお分かりの通り一過性のブームではなく、イノベーションです。
1995年にマイクロソフトのWindows95が出て、一気にパソコンでのビジネス活用が当たり前になりました。
2000年代、アップルからiPhoneが出て、通信手段も何かも変わりました。
この生成AIはそれ以上に大変革だと指摘する識者もいます。
なのに、多くの中小企業経営者は
⑴有料版機能を社員全員が使うと、コストが高い(無料版は精度が低い)
⑵学習されないかセキュリテイが不安だからしない
⑶プロンプト(指示文)をイチイチ考えるのが面倒
⑷独自のカスタムChat(MyGPTs)の設計の仕方が分からない
⑸AIを業務の仕組みに入れず、調査程度しか使っていない
こんな状況なのです。
しかし、こういう中小企業経営者の本音は違うところにあります。それは
⑴社長に知識がないから導入に後ろ向き(分からないからやらないというネガティブな選択)
⑵AIを使おうとしない社員の「訳知り顔」の反対意見に屈している
⑶大企業は導入していても、知ってる他社もまだ手付かずだから安心している
⑷AIを使わないでも、何とかやっていけるという根拠なき慢心
⑸スマホやWindows95が一気に変えた世界以上の大変革なのに、感度が鈍い
会計事務所は自ら生成AIを使うだけでなく、こういう経営者にも「生成AIの必要性と有効性」を説く責務があります。
会計事務所が顧問先経営者と一緒に生成AIを使って、一緒に経営を前に進める姿こそ、今後の会計事務所の在り方だと思うからです。
3,税理士・監査担当者が生成AIで経営支援を行う基本姿勢
では、会計事務所が生成AIを使う基本姿勢とはどういうものか?
ここでは経営支援などの付加価値づくりに関して考察したいと思います。
現在当社も4つの会計事務所に対して定期的に生成AIを活用した経営支援技術指導をしています。
そこでも行っているのは
⑴生成AIの成果を出す為のプロンプト技術とヒアリング技術
⑵月次試算表分析、決算書分析などの過去分析
⑶SWOT、KPI、経営計画や商品開発、顧客提案などの未来分析
⑷事業承継、人事評価、人材育成などでのAI活用
生成AIで単発プロンプトを使っても、それなりの回答は出してくれますが、やはり精度が低い。
それはプロンプトの質に直結した「ヒアリング能力」です。
「生成AIにはヒアリング能力は関係ないだろう。AIが考えるのだから・・」と思っている方は、おそらくいつまでもAI活用レベルは上がらないでしょう。
と言うのも、プロンプトに入れる情報はより詳細でより段階的でよりリアルな表現が求められるからです。
一般論の生成でよけれ、そこまで神経質にならなくてもいいでしょうが、所詮一般論の範囲の生成しか出ません。
だから、生成AI活用を監査担当者に教育したければ、「ヒアリング能力」と並行する事が望ましいのです。
4,生成AI時代に変わる会計事務所業界の勢力図
生成AIを使う事で、様々な業界で勢力図が変わると痛感します。
会計事務所の場合、プロンプトが上手くて、経営者の様々なニーズに即AIで答えられる若手の会計事務所にも大きなチャンスがあります。
反面、歴史のある中規模の会計事務所で生成AI活用がいまいちのところは、良い顧問先や若手経営者の顧問先から見限られる事が増えます。
そして、超大手の会計事務所は生成AIとのパッケージで様々な提案を行い、中規模以上の有料顧問先を高いフィーで獲得していきます。
と言う事は生成AI活用に消極的な会計事務所には、低価格の顧問料で、高齢化した経営者で、小規模で、未来が見えない零細企業ばかりが顧問先になり、事務所生産性も低く、賃金も上げられず、よどんだ事務所風土になっていく「負のスパイラル」が待っているかもしれないです。
これが戯言か虚言か真実かは、数年後に分かるでしょう。
だから、職員が数名から数十名規模のいわゆる「普通の会計事務所」こそ、生成AIで差別化を図る必要があるのです。
生成AIを使い、かつ教える事で、これまでの顧問料単価を上げる事も出来るし、顧問先の業務効率化にも貢献できます。
そのような会計事務所なら、良い顧問先は絶対、放しません。
このパラダイムシフトを傍観者としてみて、他人が動きだしたら動く「レイトマジョリティ」になるか、他人より先に動いてリスクも取りつつ市場を取る「アーリーアダプター」「アーリーマジョリティ」になるかは、所長次第です。